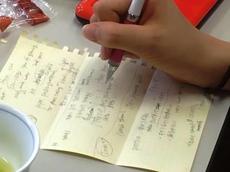- SGH報告
グローバル総合「経済発展と環境」の生徒6名が、イオン1%クラブ主催「アジア・ユースリーダーズ」(8月15日~8月22日)に参加しました。日本からは本校生徒の他、都立西高校の生徒6名の計12名が参加し、ベトナム、中国、インドネシア、マレーシア、タイの高校生とともに中国・天津で集いました。
天津市の工場爆発事故の影響が懸念される中での参加となりましたが、ゴミ問題の現状を学ぶだけでなく、解決提案に向けたディスカッションやプレゼンテーションを通じて価値観の多様性を知るとともに、各国を代表する高校生たちのレベルの高さに刺激を受ける大変有意義な1週間になりました。
また、日本・中国・タイ・インドネシア・ベトナム・マレーシア6か国の混成チームで、本校生徒3名が、それぞれ1位班、2位班 、3位班として表彰されました。